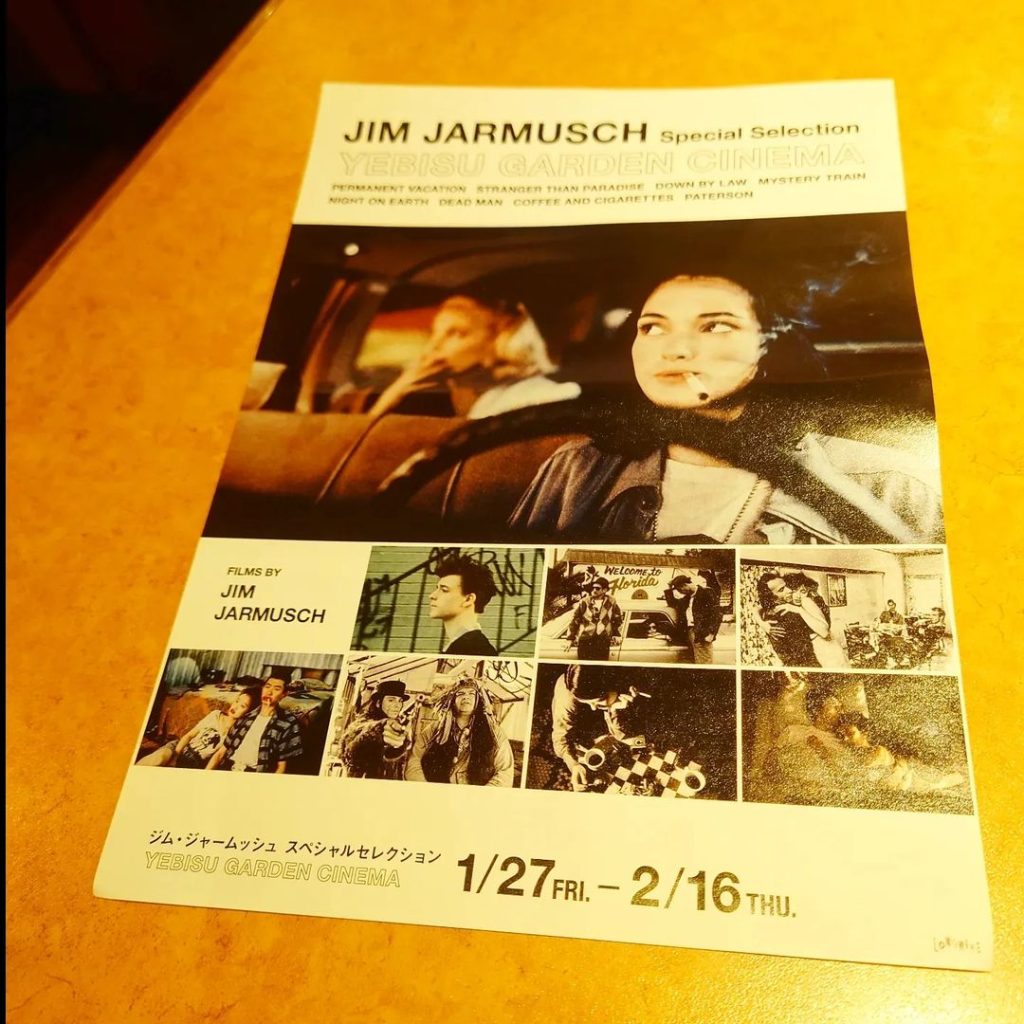好きな世界と、思いのままに直結する。
洋服や靴の写真を撮るだけで、ブランドがわかるスマホ用アプリがある。デート相手の靴を撮影すれば、ジョンロブ20万円とか、H&M2990円とか、瞬時に表示されるのだろうか。
周囲に流れている音楽が何かを教えてくれるShazamというアプリは私も使っている。空気を測定するような感覚で精度も高く、その曲が入ったジャケットデザインが綺麗にストックされる。音は商品なんだ、と改めて思ったりする。そうやって、あらゆる言葉やイメージが検索できるようになって、検索できないモノやヒトの価値は高まるばかりなのかもしれない。少なくとも、検索をしなくていい時間の価値は高まっている。
映画館が価値ある場所なのは、携帯電話の使用を、画面を光らせることも含めて禁じているからだ。音楽のライブではマナーモードにするだけだし、ふだん私が携帯を完全オフにするのは映画を見るときだけ。映画を見るのは、携帯をオフにするためかもしれないな。オーディトリウム渋谷の「ビートニク映画祭」は、そんな現実逃避感をいっそう加速させるものだった。
ビートとは、1950年代〜60年代半ばのアメリカ文学界を中心に、常識や道徳に反抗した「打ちのめされた世代」。ビートニクのニクには、1957年ソ連が打ち上げてアメリカに衝撃を与えた世界初の人工衛星「スプートニク」に由来する、卑下のニュアンスがあるらしい。
上映された7本の映画のうち、特筆すべきはロバート・フランクが撮影したコンラッド・ルークスのデビュー作「チャパクア」(1966)だ。コンラッド・ルークスの2作めにして今のところ最後の作品である「シッダールタ」(1787)もよかったし、ロバート・フランクが監督した「キャンディ・マウンテン」(1987)の素晴らしさは言うまでもない。
20代前半のボブ・ディランが浅井健一のように見えてしまう「ドント・ルック・バック」(1967)や、47歳で亡くなったジャック・ケルアックってこんなにヤバイ男だったのかと驚愕する「ジャック・ケルアック キング・オブ・ザ・ビート」(1985)は言葉からのアプローチが面白く、ビートとはナイーブで饒舌なイケメンのことだったのねと膝を打つ。ケルアックは映画の中で「ビートとは何?」と聞かれて「Sympathetic(共鳴すること)」とめちゃくちゃかっこよく答えていたし、ケルアックの死を伝えるニュース映像では「ビートは、ボヘミアンとヒッピーをつないだ」とあっさり説明していたけれど。
ケルアックはインタビュー番組のスタジオで、7年間の旅をタイプライターのロール紙に3週間で書き上げたという自作「On the road(路上)」のエピローグを、緩急をつけて詩のように朗読していた。以下は朗読の最終部分。
“Nobody knows what’s going to happen to anybody besides the forlorn rags of growing old, I think of Dean Moriarty, I even think of Old Dean Moriarty the father we never found. I think of Dean Moriarty. I think of Dean Moriarty.”
(誰に何が起こるかなんて、誰にもわからない。見捨てられたボロのように老いていくこと以外は。僕は友人のディーン・モリアーティのことを考える。そして、僕らが見つけることができなかった、もう一人のディーン・モリアーティである父親のことも。僕はディーン・モリアーティのことを考える。ディーン・モリアーティ、のことを。)
最後の文はアドリブで繰り返し、感動的にしめくくった。もはや俳優レベル。映画は終わり、場内にはすすり泣きが広がったので、再び驚いた!
本題は「チャパクア」だ。コンラッド・ルークスの自伝でドラッグ映画の金字塔。薬物中毒の男(監督)がフランスのサナトリウムに収容されるが、催眠療法の過程で幻覚をみる。希有な体験を自ら演じ、実験的に記録したものなのだ。ストーリーの大枠以外は、錯乱したイメージを衝動的につなげた無茶苦茶な映画だけど、ロバート・フランクのカメラは、どの瞬間を切り取っても言葉を失うかっこよさ。音楽や女優にも心をつかまれる。
この自由奔放さは何だろう。コンラッド・ルークスは某有名化粧品会社の御曹司らしいから、交友関係を生かしたセレブなキャスティングが可能で、制作費の心配もなかったのだろう。終盤、自分を見るもうひとりの自分の視点が出現するが、CGなしのダイナミックな動線には度肝をぬかれる。アンダーグラウンドな匂いを発しながらメジャーな完成度を備え、ヴェネチア映画祭では銀獅子賞を受賞した。
アメリカと西洋と東洋、多様な世界とダイレクトにつながるこの映画は、緩衝剤を排除した、光と音の直接言語。わかりやすさを拒む一方、これほど無意識に体に響く、刺激的なわかりやすさはない。ふだん目にするものの多くが、漠然と私たちを疲弊させる理由がわかる。かっこ悪いから、まわりくどいから、ピュアじゃないから、疲れるんだ。
上映作品のひとつ、ピーター・ホワイトヘッドの「スウィンギング・ロンドン1」(1967)では、20代前半のミック・ジャガーが「他人に求められることをやりたくない」というようなことを言っていた。自分が求めることをやり、嫌われても認められたら最高だ、と。
2014-4-2