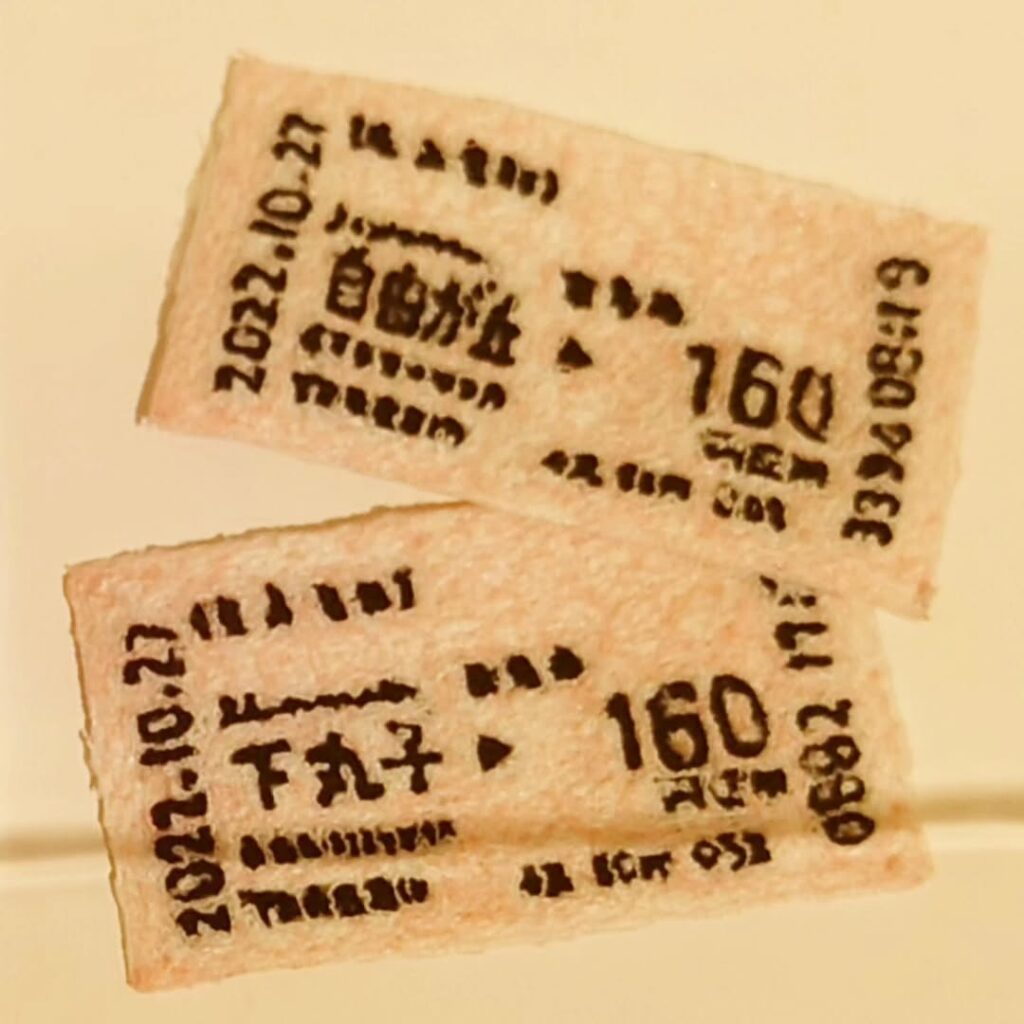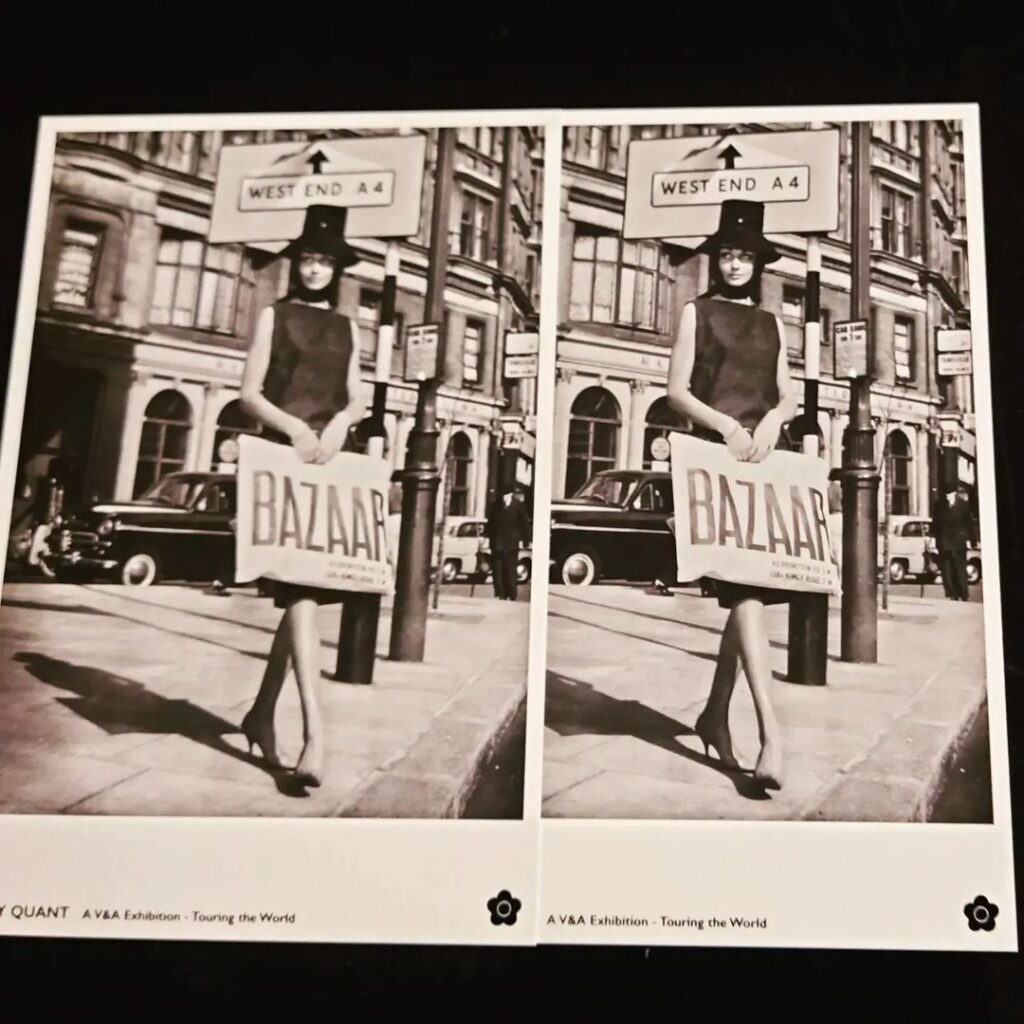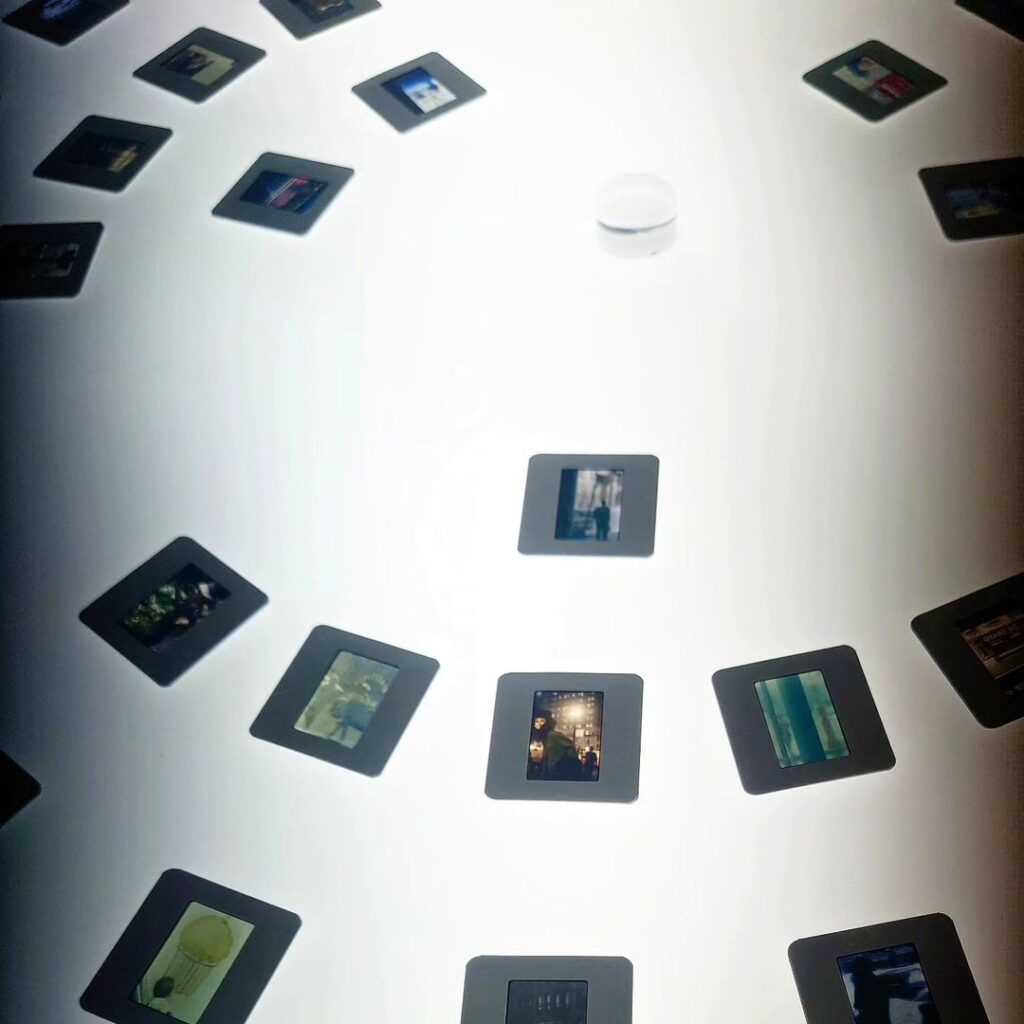幸福の絶頂にあるようなときでも、それに対して深い悲しみ、という支えがなかったら、それは浅薄なものになってしまう。― 河合隼雄
戦後ドイツを代表するアーティストといわれるアンゼルム・キーファー。その作品は一元的ではなく、繰り返し物議を醸してもきたが、さまざまなタブーに挑んだ過激な作品であることは間違いない。永遠の廃墟のような静謐な佇まいでありながら、うっかり素手で触れればヤケドしてしまいそう。だが、厄介なことに美しい。
今年は、日本で26年ぶりとなる展覧会「Opus Magnum(錬金術)」が、北青山のファーガス・マカフリー東京で開催された。ガラスケースに入った繊細な作品が並んでおり、不覚にもときめいた。見るからにヤバいモチーフもあったけれど、ガラスケースに入っているから安心、ともいえた。
キーファーと同じく1945年生まれのヴェンダースが撮った映画「アンゼルム“傷ついた世界”の芸術家」(2023)では、重厚かつ巨大な作品をたくさん見ることができる。映画だからガラスケースがなくても安心だが、3D&6Kの迫力に圧倒された。固有の名前はあるが顔のない白いドレスの女性像たちや、空に開かれた孤独な翼のモニュメント。画材とはいえない素材が厚く塗り込められ、焼かれ、ただれ、はがれた絵画の数々……
この映画は、キーファーの幼少期から現在にいたるまでの創作の旅であり、ドイツの重い歴史を掘り起こす旅でもある。キーファー本人が登場するほか、青年期を実の息子が演じ、幼少期をヴェンダースの姪の息子が演じている。
とりわけ印象に残るのが、南仏バルジャックの広大なアトリエ施設「ラ・リボーテ(La Ribaute)」。1992年、かつて養蚕工場だった40ヘクタール(富岡製糸工場の7倍以上)の土地をキーファーが買い取り、いくつもの建物や塔を建て、地下にトンネルを掘ったという。
映画の中では、本人が建物の内外を自転車で軽やかに走り回り作品をチェックしていたが、2022年春からは、2時間半のガイド付きツアーという形で一般公開が始まったようだ(車椅子可)。
そして来春(2025年3月下旬〜6月下旬)は、京都の世界遺産・二条城で新作の展覧会が開催される。庭園の一部も会場となり、アジアにおけるキーファーの個展としては過去最大規模のものになるらしい。大阪万博と重なる時期だが、とりあえずこっちだわ。
2024-7-14