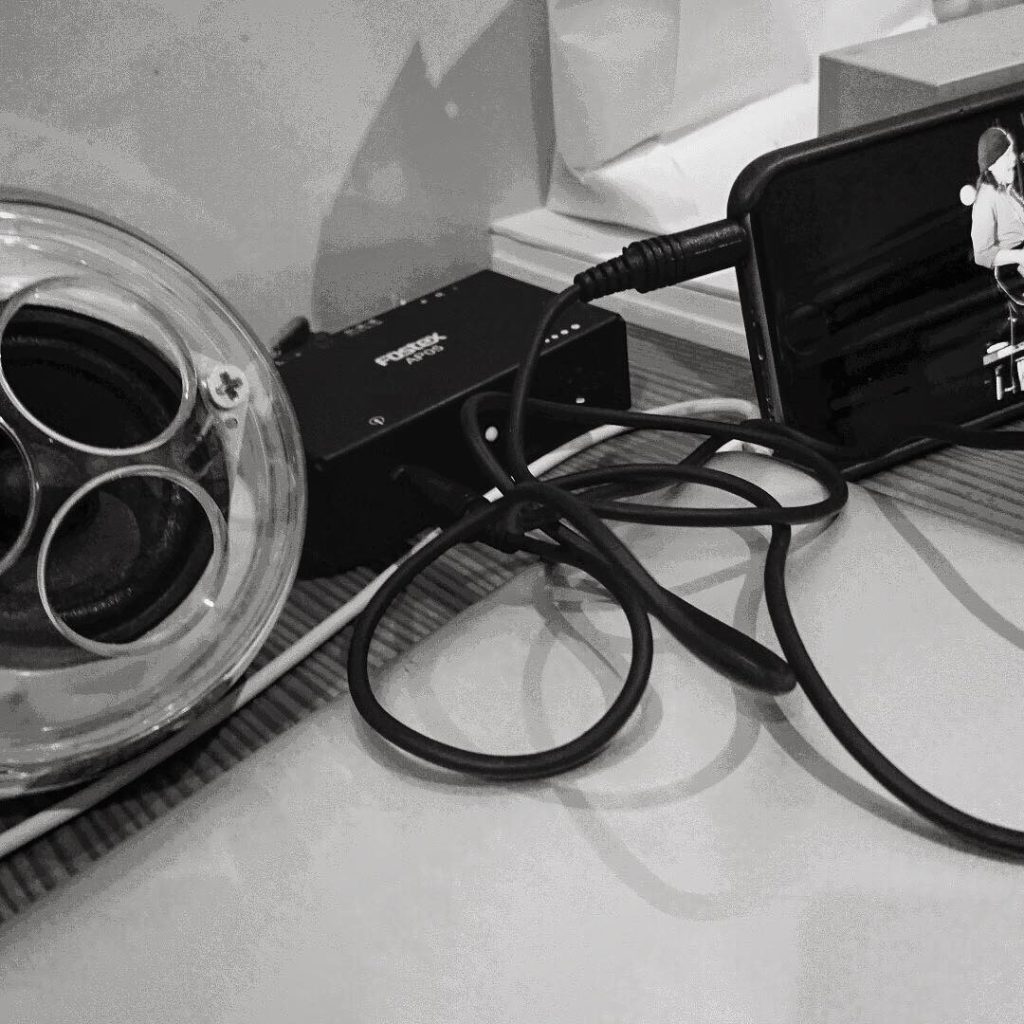帰るための旅や、目的地をめざす旅は、つまらない。
ボブ・ディランの映画なんていっぱいあるのに、なんで今さら? しかも3時間半!
だが、ちらっと目にしたモノクロのスチール写真は、公開中のほかの映画と比べると素晴らしすぎて、劇場に足を運ばずに済ますわけにはいかなかった。
現在のボブ・ディランの語りをベースに、アメリカとボブ・ディランの60年代くらいまでを検証するこの映画は、回顧的ではなく現在進行形。音楽がどうやって受け継がれていくかに焦点をあてたものだった。彼はフォークやロックの創始者というわけじゃなく、継承者の一人に過ぎない。それは、ごく普通の若者の軌跡のように見えた。ロックとは素直さ。かっこよさとは純度。そう断言したくなる理由は、彼の原点がバンドではなくソロだからだ。
昔の映像はもちろん、現在のボブ・ディランのかっこよさといったらどうよ? 彼は今もノー・ディレクション・ホーム、道の途中なのだ。「たいした野心があったわけじゃないが、自分のホームを見つけたかった」というような、みずみずしい言葉にあふれた10時間におよぶインタビューは、長年の友人が撮ったものという。D.A.ペネベイカーの「ドント・ルック・バック」(1967)のほか、アンディ・ウォーホルやジョナス・メカスによる映像も登場し、イタリア系アメリカ人監督、マーティン・スコセッシのセンスが光る。
監督はインタビューの中で「今、世の中で起きているあまりにもたくさんのことによって自分自身を吸い取られるな」「ただ人が話をしているだけで、すばらしいロードムービーになりえるんだ」と言っていたが、ボブ・ディランが普通に話しているだけで、観客は心洗われてしまうのだから参っちゃう。人はこんなふうにしゃべればいいし、こんなふうに生きればいい。でも、それが難しいから、彼の発言のひとつひとつにクギづけになる。私たちの体はふだん、紋切り型のカサカサした安っぽい言葉に埋もれ、血が出そうになっているんじゃないだろうか。
ポリティカルソングの旗手として喝采を浴びたボブ・ディランがエレキギターを手にしただけで、ライブはブーイングの嵐。「商業的なポップミュージックじゃなくてフォークを聴きにきたんだ」と怒るファン。「この曲はどういう意味なのか?」と迫るマスメディア。しかし、今となってはジャンルなんてどうでもいいし、彼の詩に「意味」なんてない。ビート詩人アレン・ギンズバーグが「激しい雨」を聴いて自分もずぶ濡れになったと語るシーンや「ライク・ア・ローリング・ストーン」は50番まで歌詞があったという事実にこそ意味がある。ボブ・ディランは7年連続でノーベル文学賞候補になっているらしいけど、その理由がわかる気がした。
ファンは勝手だとか、マスコミは馬鹿だとかそういうことじゃなくて、通りすぎる景色というのは、自分とは関係ないことがあまりにも多い。困惑しながらも、そんな状況に対処するボブ・ディランの姿にはしびれてしまうけれど、心奪われるものだけに影響を受けていれば前を見失うことはない。インチキなものに取り囲まれていても、取り込まれないで生きることは可能なのだと、彼は、全力で示した。
How does it feel どんな気分?
To be on your own ひとりぼっちで
With no direction home 帰る場所もなく
Like a complete unknown だれにも知られず
Like a rolling stone? 転がる石のように生きるのは
*シアター・イメージフォーラム、シアターN渋谷、吉祥寺バウスシアターで上映中
2006-01-26