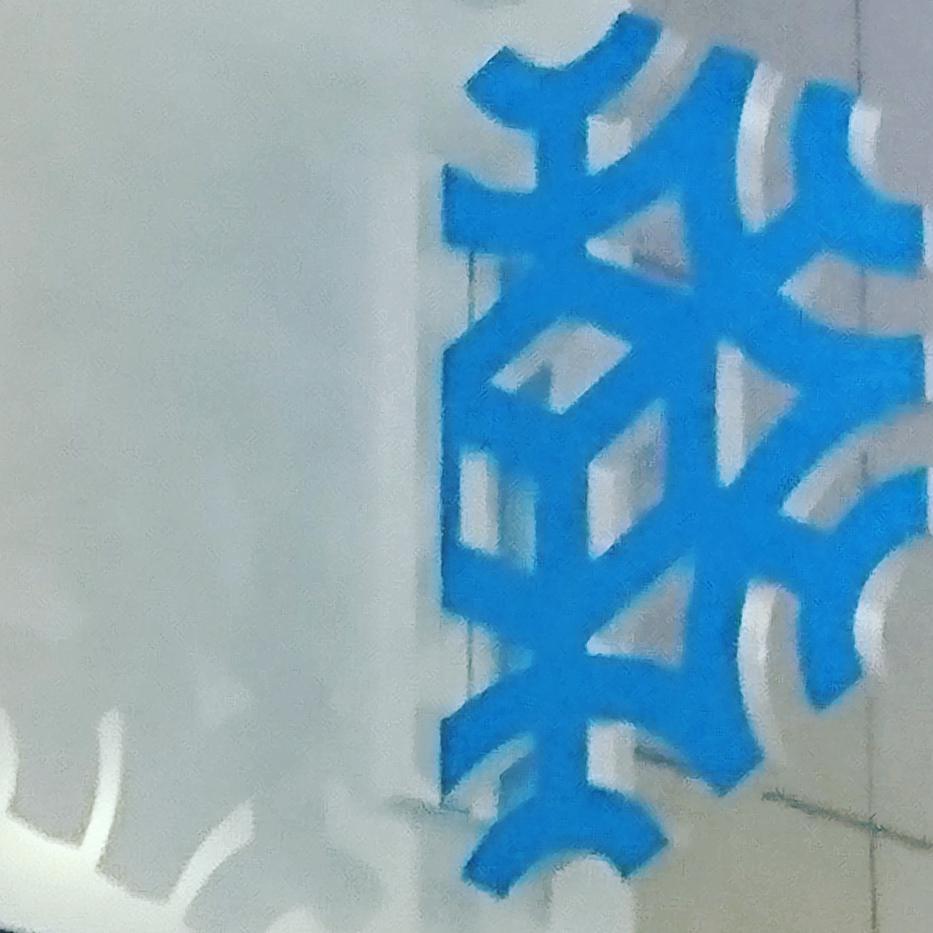雪印より美しい、偶然の結晶。
「平行線は無限遠点で交わる」といえば、地球上の経線が極点で交わるという非ユークリッド幾何学の話。
「無限遠点」を「かなた」という一般的な言葉に翻訳するのがコピーライターの仕事だと思う。
「平行線は無限のかなたで交わる」と題されたドイツのメディア・アーティスト、カールステン・ニコライによる展示は、無と有、音と映像、サイエンスとアートなど、異質の概念が出会うピュアな瞬間を私たちに体験させてくれる。
人工雪をつくり結晶を観察する装置「スノウ・ノイズ」が印象的。大きな試験管をボックスに差し込み、ひたすら待つ。15分で結晶が見え始めるとあったが、忍耐力のない私は、カフェのあるB1のオンサンデーズに降りていった。実験室における15分後は、私にとっては無限のかなたなのだ。
30分後に戻ると小さな結晶ができていた。隣の試験管の堂々たる結晶に比べるとひ弱だが、生まれたての雪はたぶん、生まれたてというだけで美しい。しかも、見たことのない形だ。私は偶然の産物である、この不完全な形を忘れない。
カールステン・ニコライは、雪博士といわれた物理学者、中谷宇吉郎(1900-1962)の本にインスパイアされ、この作品をつくったという。中谷宇吉郎は、世界で初めて人工的に雪の結晶をつくった人。1938年に刊行された「雪」には、「針状結晶」「雲粒付結晶」「無定形」など詳細な分類図がある。雪の結晶とは、雪印マークのような「立体六花型」だけではないのだ。
「(十勝岳では)これほど美しいものが文字通り無数にあってしかも殆ど誰の目にも止らずに消えてゆくのが勿体ないような気が始終していた。そして実験室の中で何時でもこのような結晶が自由に出来たなら、雪の成因の研究などという問題をはなれても随分楽しいものであろうと考えていた」(中谷宇吉郎「雪」岩波文庫)
中谷宇吉郎の研究の引き金となったのは、雪の写真家として知られるW・A・ベントレー(1865-1931)の写真集「snow crystals」(1931)である。雪の結晶の古典というべき本だが、3000枚の結晶写真をぼーっと眺めるだけで圧倒される。最後のほうに不完全な結晶たちが集められており、その部分がやはり、いい。
カールステン・ニコライ展では、雲の写真も美しい。ドイツからイタリアに向かう飛行機から撮ったその写真を彼自身は「石庭のよう」と表現する。雲もまた偶然の産物なのだ。美しい形は、世界中で絶えず生まれては消えてゆく。これほどポジティブでシンプルでピュアな、世界の切り取り方があるだろうか?
音の実験室といわれる彼のライブ&DJにも行ってみた。ふだんは洋書店&カフェであるオンサンデーズのB1フロアが、水曜の夜にはクラブになるのだ。吹き抜け構造と書棚のおかげで音がいいし、彼が主宰するレーベル「ラスター・ノートン」のCDも揃っている。
青山や渋谷では今、セレクトショップ+カフェレストラン+DJといったスタイルが流行しており、おしゃれ系の店には、必ずターンテーブルとDJブースがある。1990年マリオ・ボッタによって建てられたワタリウム美術館は、そんな現在形の街のスタイルになじんでおり、大勢の客を動員するには非効率だが、今回の企画展には、まさにふさわしい。非効率だからこそ、ここには、いつか交わりそうな偶然が満ちている。
「偶然をコントロールしようとする試みは必ず失敗するだろう」とカールステン・ニコライは言う。世の中は、人知や計算で制御できないことだらけなのだから、無理にあがくことはないし、悲観することもない。
だって、平行線はいつか必ず交わるのだから。
(9月6日まで)
2002-06-12