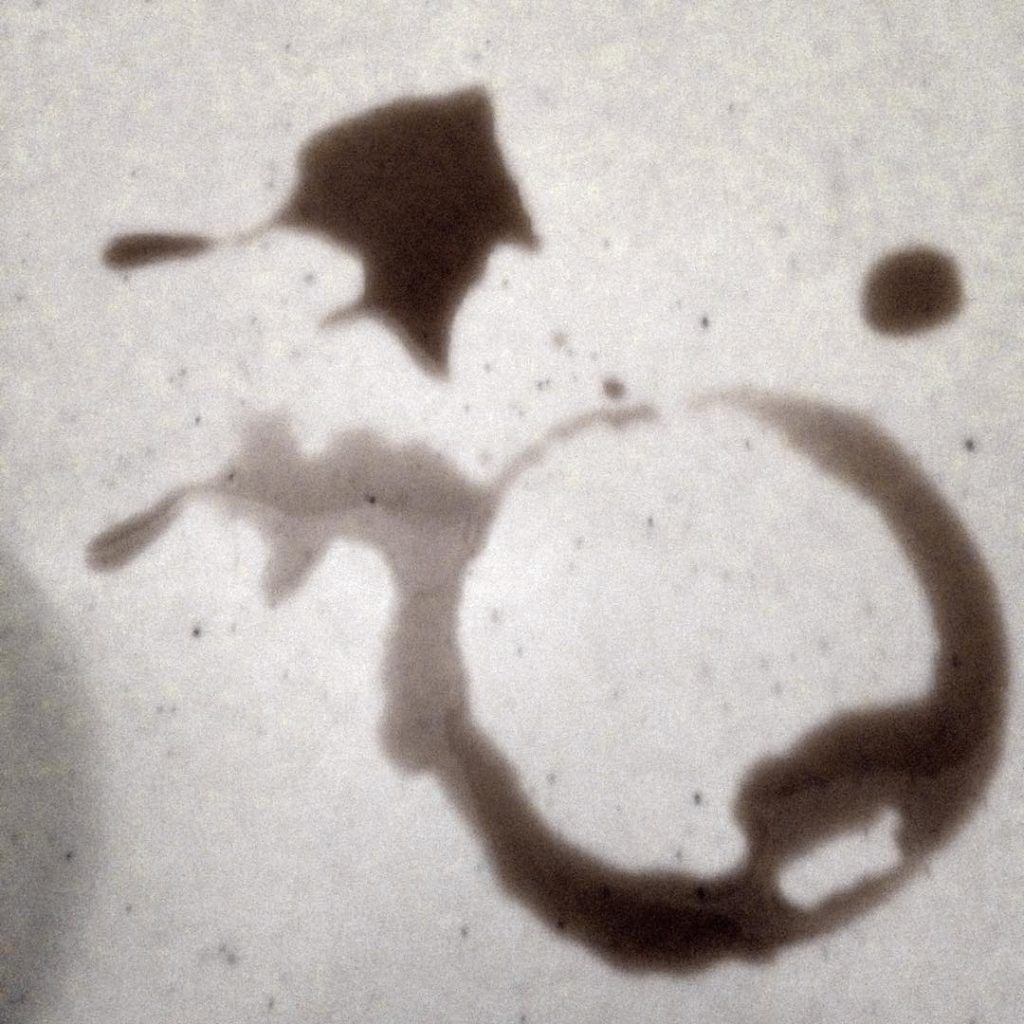おっさんの匂いがしない役所広司。
「この映画、見たって言うのやめよう。だって気持ち悪いじゃん」
上映直後、橋本愛タイプの子が、小松菜奈タイプの子にそう言い放った。そのまま映画の宣伝コピーになりそうな言葉だ。
こんな気持ち悪い映画を宣伝したくないから?
こんな気持ち悪い映画を好む人間だと思われたくないから?
たぶん彼女は友達に宣伝するだろう。「気持ち悪いよー、見ないほうがいいよー、『告白』と違うからー」って。https://www.lyricnet.jp/kurushiihodosuki/2010/06/28/843/
中島監督は『告白』に安易に感動したファンの感受性を試しているのだろうか。意味を剥奪するスピード感と残虐さは、もはやレッドカードレベル。絶賛されるとブチこわしたくなる男の子の衝動か。「ボクのこと好き?本当に?ボクってこうなんだよ?ちゃんと見てくれてる?」と果てしなく鎌をかけられるような悪夢。主役のふたり、高校生の加奈子(小松菜奈)も父親の藤島(役所広司)も相当くるっているけれど、それ以上に心配になるのが監督の病だ。
アメコミとバイオレンスとファンタジーとガールズポップをコラージュするセンスは笑えるほど素晴らしいし、残虐さを美しいメロディーで中和させるテクニックは中毒性をはらむ。迷いのない編集は痛快で、クリスマスの狂騒や住宅メーカーのCMの虚飾を容赦なく暴くあたりにCMディレクターとしての破壊力が冴える。
監督が惚れ込んだキャラクターである加奈子は「相手がいちばん言ってほしいと思うことを言い、引きつけて、メチャクチャにする」女。私は最近、星野智幸の『夜は終わらない』と村上春樹の『女のいない男たち』の書評を20〜30代女性向けの媒体に書いたが、これらの小説には加奈子に似た女が登場する。今、この手の古風な悪女が旬なのだ。成熟世代の男たち(中島哲也、星野智幸、村上春樹)がコントロール不能な女に抗いがたい魅力を感じ、自分もまた同種の衝動を抱えていることに気づく。女たちが、そういうねじれた状況を許容すれば世の中は楽しくなるのかなと思い、私は本を紹介する。
音楽のミスマッチな使い方は『アッカトーネ』(1961)の暴力シーンでバッハのマタイ受難曲を使ったパゾリーニのようだ。美しい旋律を唐突に分断するゴダールとは異なり、中島監督は音楽をファッションアイテムとして取り入れる。音楽プロデューサーの金橋豊彦氏によると、中島監督が提示した選曲の条件はスタイリッシュであること。さらに考慮すべきこととして、加奈子は「美しく、せつなくある一方で、狂った感じ」、藤島は「古臭く、男臭く、でもおっさんの匂いはしない」という方向性が求められたという。
血まみれになって汚れていく脂ぎった藤島の暴力を、かろうじて最後まで見ることができた理由はここだったのか。監督は藤島から「おっさんの匂い」だけを巧妙にそぎ落としていたのだ。それは「かっこわるい保身」と言い換えてもいい。この映画は、かっこわるい保身くささが主役の現実世界よりは、はるかにましなのである。
藤島のスーツの色に、黒ではなく白を選んだスタイリストの申谷弘美氏、坊主ではなくロンゲを選んだヘアメイクの山﨑聡氏。この2人のおかげで、藤島がイエス・キリストのように見えるシーンが生まれた。そう、彼は、世の中の十字架を一手に引き受けたヒーロー! 私には確かにそう見えたのだけど。
でもやっぱり、この映画、見たって言うのやめよう。だって気持ち悪いじゃん。
2014-6-28