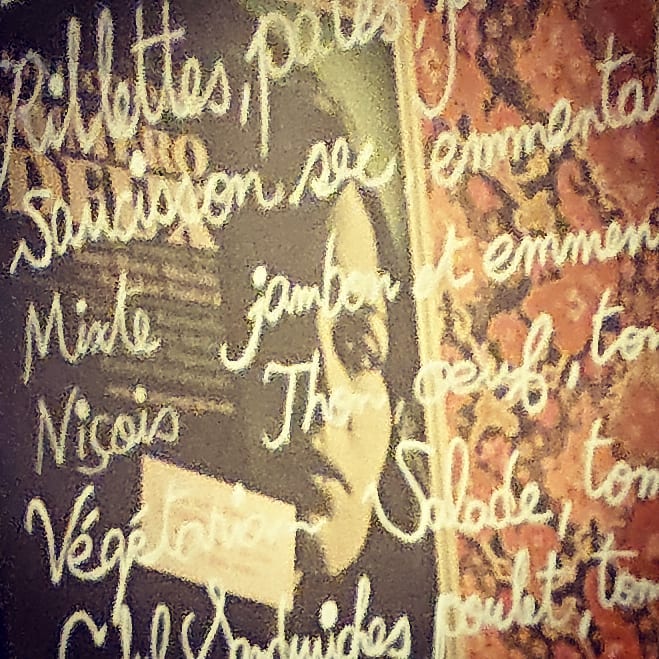あるがままの真摯さに、しびれる。
大好きな作家にインタビューする夢が叶い、彼女が、定型の面白さを注意深く排除することで、純粋に面白い作品を書いていることを知った。天の邪鬼ということではない。それこそが、世界をあるがままに受け止める素直さなのだ。
『アスファルト』(2015・サミュエル・ベンシェトリ監督)の世界から抜けられずにいる。何らかの喪失を抱え、心理的に迷子になった団地の住人たちについての映画だ。不時着したNASAの宇宙飛行士を、言葉も通じないのに息子のように世話する老女。隣に引越してきた《わけあり女優》を、ごく普通に助ける《美しい10代の青年》。団地の中で迷走し、外へ出ることで《運命の看護師》と出会う中年男性。伝わるはずがないという前提で、奇跡的にコミュニケーションが成立する瞬間が描かれていた。それは、自らの弱さを自覚し、率直に、対等に、いちばん大切なことを伝え合う、愛以前の美しい交流に見えた。
こんな世界に浸っていたくて、《運命の看護師》役のバレリア・ブルーニ・テデスキが重要な役を演じる『人間の値打ち』(2013)や、《美しい10代の青年》役のジュール・ベンシェトリの祖父が主演する『男と女』(1966)を見たが、その延長で、またまた凄い作品に出会ってしまった。《わけあり女優》役のイザベル・ユペールが、母であり女でもある戦場カメラマンを演じる『母の残像』(2015)だ。
ひとことでいえば、定型を排除した家族愛の映画。最初のシーンで、赤ん坊の小さな手が大人の人差し指をつかみ、その指が若い父親(ジョナ)のものであることがわかる。妻が出産したばかりの病院。心温まる誕生シーン? いや、そういう普通の物語じゃない。
誰もが内密の不安を抱えながら、大事な人を心配している。そこに上下関係はない。誰かが誰かに向けるまなざしのすべてが真摯であるという真っ当なことが、見たことのない表現方法で描かれている。見て見ぬふりをしながら、愛する人を、そっと見守っているのだ。見て見ぬふり、わかっているのにわかっていないふりが、この映画では愛になる。衝撃だった。
ジョナの母親は、3年前、57歳で亡くなった。クルマの事故ということになっているが、自殺のようでもある。ジョナは、母親の遺品の整理という名目で、父親と弟が暮らす実家に、妻子を連れずに戻ってくる。
母親の死の真相を知らない弟コンラッドは、何をしでかすかわからない、妄想まみれの危うい思春期を生きている。だがジョナは、馬鹿だと思っていたコンラッドの才能を見出すのだ。個性的な弟が、その芽を摘むことなく今を生き抜くための、兄の的確なアドバイスが泣ける。そして弟もまた、兄の不安を見抜いているという事実。
コンラッドが、叶う見込みのない恋の相手とパーティで話をし、彼女を家まで送るシーンは忘れられない。家に着くころには夜が明けている。一緒に歩いた魔法の時間を彼は忘れないだろう、ということを、あまりにも、あるがままに描き切った神聖な情景。その時間の美しい希望は、簡単に成就するわけではないが、記憶は永遠だ。真摯であるべきときに真摯であることによって、私たちは、かけがえのないギフトを受け取れるのだろう。
愛は永遠じゃない。形を変える。でも、その形を焼き付けることはできる。たとえばこの映画のように。
2016-11-29