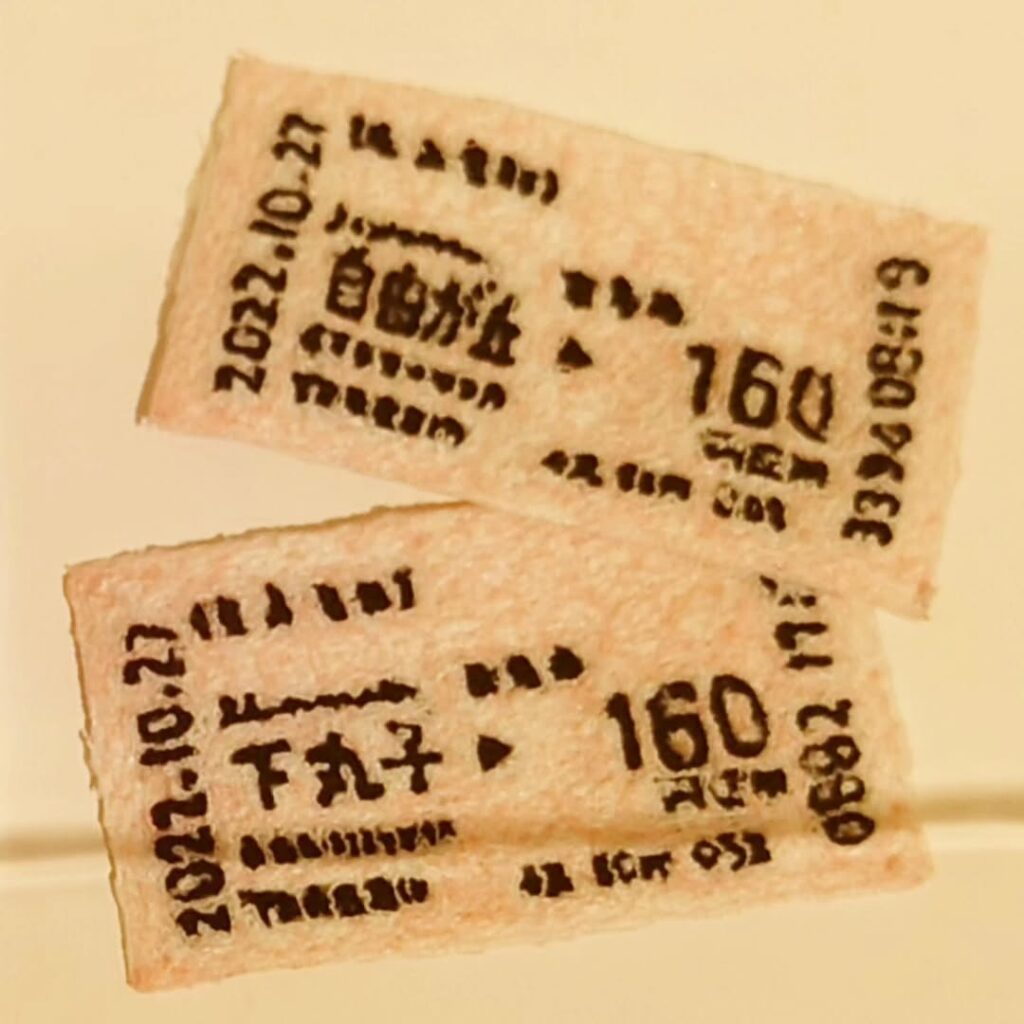こわされる快感!
新鮮なニュースはインターネットで届くけど、斬新なメッセージは不意に過去からやってくる。
1967年の映画が、2002年の現実にくさびを打ち込む驚き!
ポップでキッチュでおしゃれで笑えるポリティカル・ロードムービー。それが「WEEK-END」だ。
悪夢のような週末は、こんなシーンから動き出す。遺産目当てにオープンカー(ファセル・ベガ)で妻の実家へ向かう夫婦。彼らはアパートの駐車場を出発する際、バックした勢いで後ろのクルマ(ルノー・ドーフィン)にぶつけてしまう。子供が騒ぎ出したため、夫は金を渡してなだめるが、彼は再び騒ぎ出す。かくしてルノーの持ち主である子供の両親が登場し、各自がペンキ、テニスラケットとボール、弓矢、猟銃といった武器を駆使しての乱闘となる。「成り上がり!」「ケチ!」「コミュニスト!」となじりあう2家族。徹底的にふざけたシーンだが、こんな些細なケンカこそが、あらゆる争いの原点なのだ。
延々と続く渋滞。おびただしい死体と事故車。非現実的なシーンの連続は、嘘っぽいけれど嘘じゃない。週末って本来こういうものなんじゃないの? 実はみんな知っている。気付かないふりをしているだけ。
さまざまな困難が夫婦を襲い、実家への道のりは遠い。親を殺すという目標があるから、夫婦は力を合わせて生き延びる。が、本当はそれぞれに愛人がいて、遺産を手にした後は互いに死ねばいいと思っているのだ。クルマが事故った時、妻が絶叫する理由は、大切なエルメスのバッグが燃えてしまったから。このシーン、コメディなんかじゃない。人間って本来こういうものなんじゃないの? 実はみんな知っている。気付かないふりをしているだけ。
妻が男の死体からジーンズを脱がして履こうとすると、夫は「それを脱いで道路に寝転んで足を開け」と言う。ヒッチハイクのためだ。妻が通りすがりの男に乱暴されたときも夫は平然としているのだが、最終的にこの夫婦、どっちが勝つか?ラストシーンは、一見残酷なように見えて、ちっとも残酷じゃない。 弱肉強食って本来こういうことなんじゃないの? 実はみんな知っている。気付かないふりをしているだけ。
屋外で、ピアニストが下手なモーツァルトを弾きながら「深刻な現代音楽」を批判するシーンも印象的。これって、NYの個人映画作家たちへの当てつけだろうか? その代表的存在であるジョナス・メカスは1968年、「メカスの映画日記」の中で、「(ゴダールは)いまだに自由になるための最後のきずなを断ち切っていない」「いまだに、資本主義の映画、親父の映画、悪質な映画と通じ合っている」と断じている(by ミルクマン斉藤氏)。
たしかに「WEEK-END」は「深刻な現代音楽」(個人映画)ではないし「モーツァルト」(ハリウッド映画)でもない。商業映画へのアンチテーゼを同じ土俵で提示した「下手なモーツァルト」であり、モーツァルトの和音に基いた「POPな現代音楽」なのだと思う。
世の中のキレイ事やガチガチの文法を鮮やかに解体するこの映画は、感動や趣味や思想を一方的に押し付けたりしない。ただひたすら、こわすのみ。だから、見終わった後、とても軽くなれる。こんな映画がGWに上映されるなんて面白すぎ。渋滞の中をクルマで出掛けるか?この映画を観るか? 夢のような選択だ。
個人的には、登場人物の一人ジャン=ピエール・レオーのごとく、ホンダS800でエゴイスティックに逃げ切る旅が楽しいと思う。だけど、この映画を観てからお気に入りのクルマを選んでも遅くはない。人生100倍楽しくなることは確実!
*1967年 仏=伊合作 仏映画
*渋谷ユーロスペースで上映中
2002-05-03
amazon