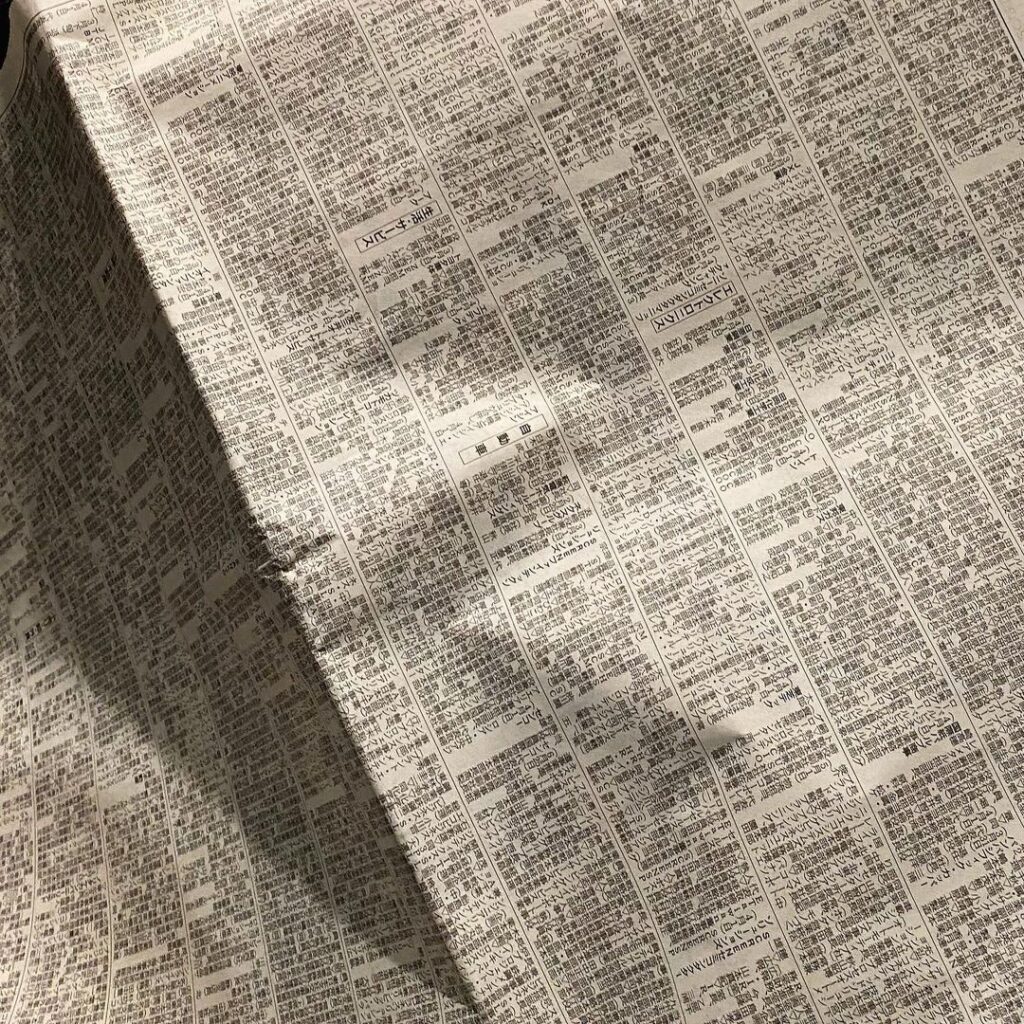見えない空気を凝視する 2
2015年10月8日、スウェーデン・アカデミーは、ベラルーシのロシア語ノンフィクション作家、スベトラーナ・アレクシエービッチ氏(67)にノーベル文学賞を授与すると発表した。ノンフィクションでの受賞、ジャーナリストとしての受賞、ベラルーシ人としての受賞、いずれも彼女が初めてだそう。500人の証言をもとに書かれた『チェルノブイリの祈りー未来の物語』(松本妙子訳・岩波書店2007年初版)で知られている。
「未来の物語」というサブタイトルの予言は的中した。アレクシエービッチ氏は、福島第一原発の事故直後、改めてこうコメントしていた。「わたしは過去についての本を書いていたのに、それは未来のことだったとは!」(中日新聞10月9日)
さらに日本の映画についてのコメントもあった。「原発の爆発が描かれた黒澤明監督の『夢』(1990)はまさに予言でした」(朝日新聞デジタル版10月8日)
『夢』は、黒澤明監督が見た夢を映像化した8話のオムニバス映画。アレクシエービッチ氏が言及したのはその中の『赤富士』だ。原発が次々と爆発し、富士山が真っ赤に溶解する中「狭い日本だ、逃げ道はないよ!」と叫びながら逃げまどう人々。人類は放射性物質を着色することに成功しており、赤はプルトニウム239、黄色はストロンチウム90、紫はセシウム137。だがそれは「知らずに殺されるか、知っていて殺されるかの違い」に過ぎないのである。
1990年にこの映画を見た時は悪夢だと思った。2011年にYouTubeで見た時は現実だと思った。2015年の今、もう一度見たら未来だと思った。黒澤明監督は、見えないものが見えても再び見えないふりをしてしまう愚かな私たちのために、放射性物質に毒々しい色をつけたのだろう。知っていて殺される未来が、迫っているのかもしれない。
着色された放射性物質が、最後に残った男女と2人の子供を包みこみ、この悪夢は終わる。いや、終わらない。『夢』という映画は、それぞれの夢が終わらずにつながっていく。
2015-10-10