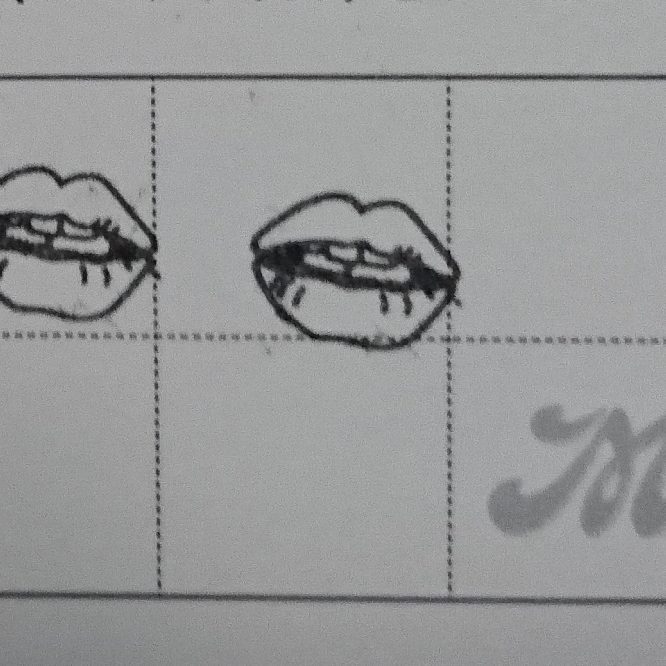ダメな男は、美しい?
今さらなぜ、1968年の五月革命の話なんて撮るのか。フィリップ・ガレルは、当時のパリの風俗を完璧なモノクロのコントラストで再現した。ひとつひとつのシーンがビクトル・エリセばりの完成度で、しかも3時間という長さなのだから、あきれ果ててしまう。
主役のフランソワを演じたルイ・ガレルは、監督の息子。つまりこれは、1968年に20歳だった監督自身を、ようやく20歳になった美しい息子に演じさせたナルシス的デカダンス映画なのだ。
ヴィスコンティがヘルムート・バーガーを超越的な美しさで撮った4時間の大作「ルートヴィヒ」(1973)や、カート・コバーンの自殺直前の数日を描いたガス・ヴァン・サントの「ラスト・デイズ」(2005)にそっくり。闘争の退屈さを延々と映すシーンは、アモス・ギタイの「キプールの記憶」(2000)の倦怠そのもの。
たとえ醜い俳優でも信じられない映像美で魅せてしまう監督のことだから、フランソワの存在感は非の打ちどころがない。途中、フルでかかるニコの曲とキンクスの曲もめちゃくちゃかっこよくて、映画で音楽を使うならこういうふうに使うべきという最高のお手本だ。フランソワとリリーが恋に落ちるシーンだって、恋に落ちるってこんな感じ以外ありえないでしょうという不滅の説得力がある。さすが、ニコと長年暮らし、ジーン・セバーグやカトリーヌ・ドヌーブにも惚れられた監督、ただものじゃない。
だけど、だからこそ、フランソワがふられるプロセスは、さらにリアル度増量。彼の美しさは圧倒的だけど、フィリップ・ガレルの映画だからして、当然、ダメ男なのだった。ダメなものはダメなまま描き、うそっぽい希望を混ぜたりしないところが素晴らしい。
フランソワに似たタイプの友達が、かつて私にもいた。救いのないこの映画は、救いのない結末を迎えてしまった彼のことを思わせる。
フィリップ・ガレルは、この映画を撮ることで、20歳のころの自分に決着をつけることができただろうか。そう簡単にはいかないはず。監督は、ダメな男の映画を作り続け、私もまた、このような美しい映画を繰り返し見てしまうのだろう。現実に救いがない以上、救いのある映画なんて見たくない。救いがなく、結論が出ない映画を求めているのだ。フィリップ・ガレルがもう何十年もこういう映画を撮っているという事実にのみ、私は救われる。
2007-01-21