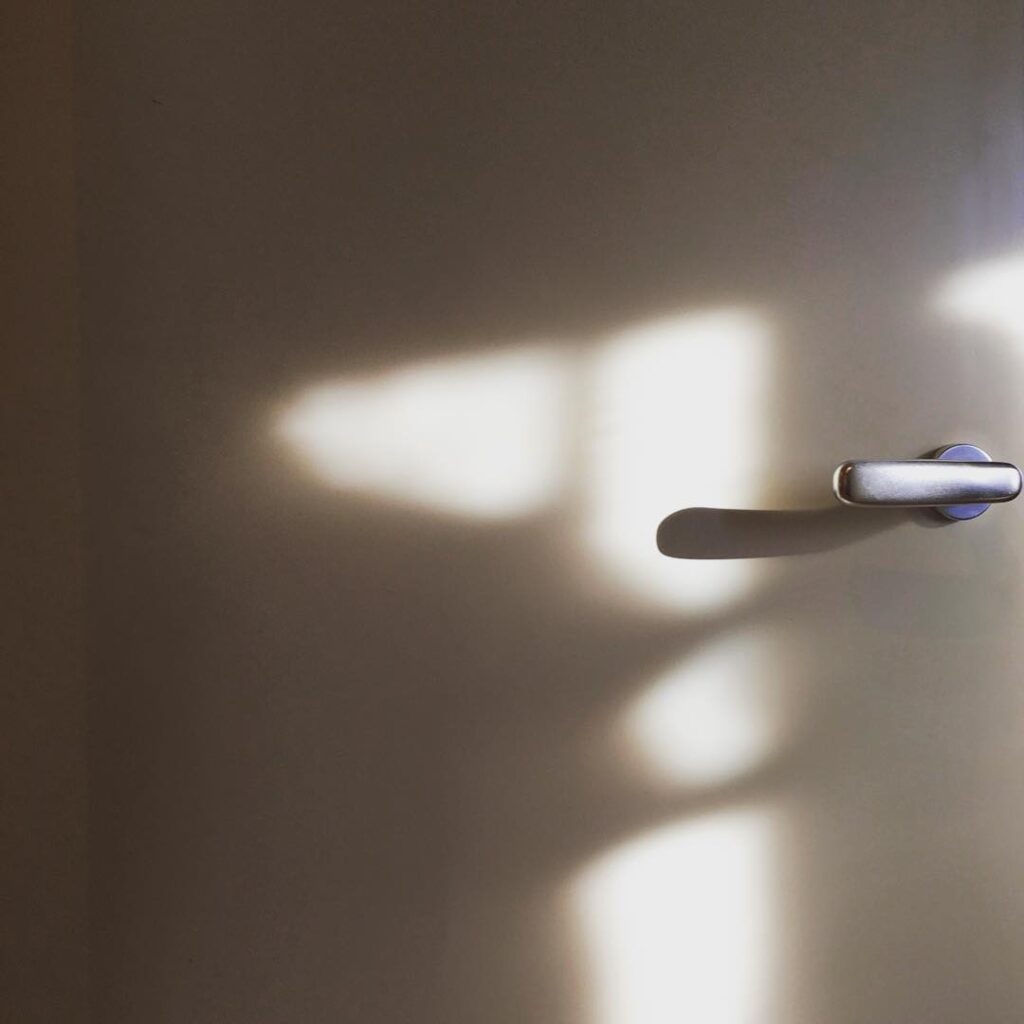美化されないから、美しい。
飲み会で、外資系銀行に勤める女子が言う。「昨夜も飲みすぎて、今日は会社休んじゃったんだけど、ここへ来るまでに何人も会社の人とすれ違って、気まずかったよー」。
保証会社に勤める男子は言う。「実家が新潟の被災地の近くで、会社の人たちから見舞い金をもらっちゃってさ。休みを取ったら、帰るの?大変だねって言われて、イタリアに遊びに行くなんて言えなかったよー」。
実際はナーバスな状況なのだろうが、彼らが楽しそうに話すので、私も笑いながら聞いてしまう。
会社の話が面白いのは、そこが「建て前」で成り立っている場所だからだ。建て前は、時に美しい―。
個人的な演技を撮るには俳優や演出が必要だが、社会的演技(=建て前)はそのまま撮影すればいい。集団の中では、誰もが特定の役割を担っており、演技することが自然だからだ。フレデリック・ワイズマンは、ある集団における人々の描写に徹することで、建て前から真実をあぶりだしてしまう。
ワイズマンのドキュメンタリー映画は、さまざまな場所で撮影される。精神異常犯罪者を矯正するマサチューセッツの刑務所(「チチカット・フォーリーズ」1967)、ハーレムの大病院(「病院」1970)、NATOのヨーロッパ演習エリア(「軍事演習」1979)、ニューヨークのモデル事務所(「モデル」1980)、ダラスの高級百貨店(「ストア」1983)、アラバマの障害者技術訓練校(「適応と仕事」1986)、黒人ばかりが住むシカゴ郊外の公共住宅(「パブリック・ハウジング」1997)、フロリダのDV被害者保護施設(「DV」2001) などだ。
「これは○○な時代を生き抜いた××な男たちの物語である―」といった説明的なナレーションや大袈裟なBGMに慣れてしまうと、世の中は感動的なエピソードだらけのような気がしてくるが、ワイズマンの映画を見ると、そんなものは実はどこにもないことがわかってしまう。つまり、そこに描かれているのは、淡々とした等身大の日常そのもの。一面的な結論を捏造しないことで、多様な現実が見えてくる。
ワイズマンと好対照をなす2人の映画監督が思い浮かぶ。1人は、キッチュな映像とミスマッチなナレーション、ずたずたに切り刻んだ音楽などを組み合わせ、よりわかりやすく人々を啓蒙するジャン=リュック・ゴダール。もう1人は、独善的な視点から世の中の構造を単純化し、ニール・ヤングやルイ・アームストロングなどの曲をまぶすことで、よりわかりやすくエンターテインメント化するマイケル・ムーア。2人の監督が自分の存在を前面に押し出すのに対し、ワイズマンは自分の存在を徹底的に消す。観客へのサービス以前に、ひたすら興味の対象を注視することから生まれる純粋な映像は、ドキュメンタリーの原点というべきもので、心洗われる。視聴率の呪縛から逃れられないテレビの人が見れば、命の洗濯になるのではないだろうか。
とりわけ、仕事をテーマにした「モデル」「ストア」「適応と仕事」の3本は美しい。モデル事務所で面接を受けるモデルたちにも、百貨店で働く従業員たちにも、職業訓練をこなす障害者たちにも励まされるし、一人ひとりのモデルに短時間で的確なアドバイスをするモデル事務所のスタッフや、確固たる企業ポリシーを語るニーマン・マーカス百貨店の経営者、一人ひとりの障害者についてじっくり討議する技術訓練校のスタッフなど、組織側の人間の社会的演技(=建て前)にも救われる。
ワイズマンは美しいものばかりを選んで撮っているのだろうか? まさか!
手術、嘔吐、凶悪犯罪…胸が悪くなるような正視に堪えない映像が一方にあるからこそ、この3本の「普通の美しさ」が際立つのだ。
2004-11-29