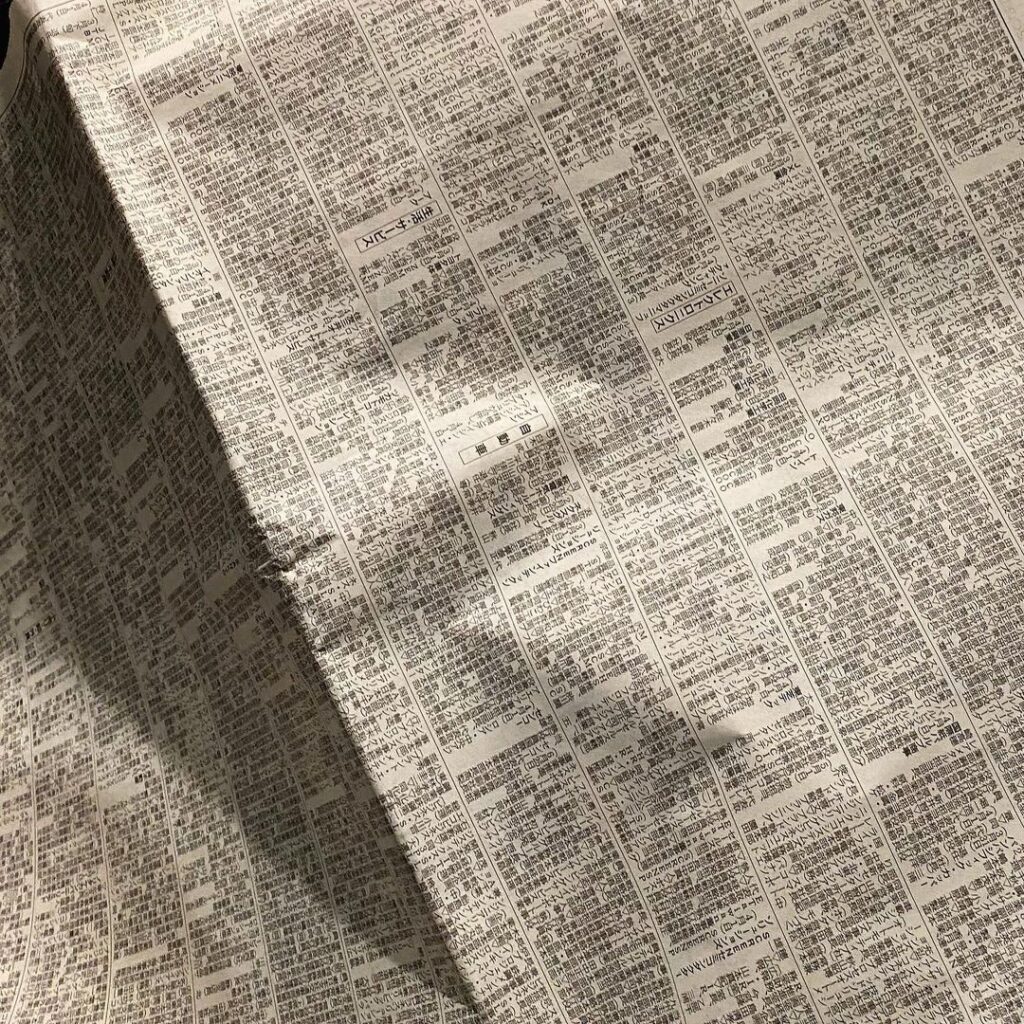被害者は、加害者になっちゃダメ。
8月25日付で発行された「本田靖春集5-不当逮捕/警察回り」をもって、本田靖春集全5巻が完結した。
全集刊行にあたっての「著者からのメッセージ」には、こう書かれている。
「ある時期から私は、『由緒正しい貧乏人』を自称するようになった。それは、権力に阿らず財力にへつらわない、という決意表明であった。いま私は不治の病を三つばかり抱えている。消えてしまった戦後民主主義のあとを追って、間もなく逝くであろう」
逝かないでほしい、と私は思う。不治の病なんて、誰でも三つくらい抱えているものじゃない?本田靖春氏も生まれたばかりの赤ちゃんも私たちも、いくつかの不治の病を抱えながら等しく現在を生きているのだ。そんなふうに勝手に思っていたい。病床の著者は今「我、拗(す)ね者として生涯を閉ず」という自伝的ノンフィクションを月刊現代に連載している。
本書には、1963年の「吉展ちゃん誘拐事件」を丹念に取材した「誘拐」(文芸春秋読者賞・講談社出版文化賞受賞)と、国の開発構想に翻弄され続ける六ヶ所村むつ小川原地区の歴史をあぶり出した「村が消えた」の2編が収録されている。どちらの作品も、関係者一人ひとりの個人的な背景に寄り添うことで、事件にトータルに迫っている。
「事件にトータルに迫る、と口ではいっても、取材の行く手に待ち受ける障碍はそれこそ数限りなく、逃げ出したい気持に襲われることもしばしばであったが、その姿勢だけは辛うじて貫いたつもりである。事実とのあいだの緊張関係を保ち続けるのは息苦しい。しかし、それなくしてノンフィクションは成立し得ないからである」
(「誘拐」文庫版のためのあとがきより)
「誘拐」を読むと、吉展ちゃんを殺した小原保もまた被害者であることがわかる。被害の根源は、彼の生まれた土地であり、環境であり、血であり、病いであり、不運であり、お金であり、弱さでもある。つきつめていえば、最後の「弱さ」のみが原因だと断言できそうだが、著者はそんな彼に同情するでもなく、糾弾するでもなく、公平な視点で事実を掘り起こし積み重ねてゆく。
吉展ちゃんは殺害され、小原保は死刑になった。殺人にも死刑にも、救いはない。唯一の救いがあるとすれば、それは吉展ちゃんの遺族の理解である。「誘拐」を原作とするテレビ番組が放映されたあと、それまで何かとマスコミ不信を口にしていた吉展ちゃんの遺族が「私たちは被害者の憎しみでしか事件を見てこなかったが、これで犯人の側にもかわいそうな事情があったことを理解出来た」という趣旨の感想を述べたという。彼らは、一方的な被害者意識を軽減することができたのだろう。
被害者意識からは、恨みや報復しか生まれない。小原保を誘拐殺人鬼へと駆り立てた元凶も、被害者意識だったのではなかったか。切羽詰った被害者意識は、一発大逆転への暗い希望へとつながる。「かわいそうな事情」を抱える人間ほど、加害者へと豹変する可能性を秘めているのだ。 そんなネガティブな連鎖の構造を断ち切ることがノンフィクションの役割なのかもしれない。
新聞紙面を眺めれば、相も変わらず殺人、虐待、横領、隠蔽の日々。どんな事件の背景にも、必ず何らかの「かわいそうな事情」があるはずとは思うものの、私たちが学ぶべきは、非常事態の中で志を高く持ち続けるにはどうすればいいか、金や権力の有無といった瑣末な状況に左右されない不変の境地を獲得するにはどうすればいいかということである。
本田靖春氏は「由緒正しい貧乏人を自称する」という答えを出した。
自らの出自に誇りを持ち、きちんとものを言いながら生きていくことだと思う。
2002-08-27
amazon