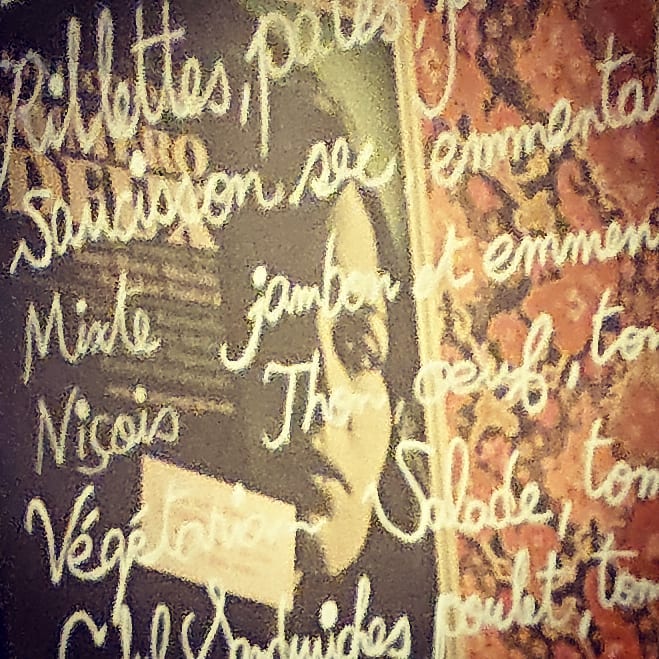女子高生が処女懐胎したら?
「背中に羽がはえた人」がスクリーンに登場すると、がっかりする。
安易な小道具を使わずに、天使あるいは天使のような人間であることを表現してくれなければ、観客の楽しみはあらかじめ奪われてしまう。「ピアノ・レッスン」も「ベルリン・天使の詩」もそうだった。
映画の前半は、ゴダールのパートナー、アンヌ=マリー・ミエヴィルの作品「マリアの本」(1984年・28分)。
主役のマリアには羽こそはえていないものの、「鋭い感覚をもつ無垢な少女」であることが過剰に説明される。自由になりたいがために夫との別居を望む妻、父母の不仲の間に立たされる少女というテーマはありきたりだし、妻がマリアを置いて別の男と外出するラストにはリアリティがない。父親を訪ねてマリアが列車で旅するあたりはいい感じだけど、マリアの友達が「うちは別居してなくてよかった」などと類型的なセリフを吐くのだから意気消沈。現実の子供なら、よくも悪くも、もう少し面白いことを言うだろう。
「鋭い感覚をもつ無垢な少女」であるマリアは、朝食のテーブルで林檎をぐちゃぐちゃにしながら唐突に眼球手術の説明を始めたり、ゆで卵の殻を首切りみたいにナイフで切り落としたり、ボードレールの「悪の華」を音読したり、マーラーを聴きながら憑かれたように踊ったりする。マリアのエキセントリックな演技はこの作品の唯一の見どころだが、母親が「何でも遊びにしちゃうのね。変な子」というような陳腐な言い方で説明してしまうため、私たちは「マリアの変さ加減」に身をゆだねることすら叶わない。そうだ、この作品は「母親のつまらなさ加減」をあらわした映画なのだ。母親が、家族のみならず、映画全体を台無しにしてしまうのだから。マリアよ、今すぐ父のもとへ行け!
後半は、ゴダールの作品「こんにちは、マリア」(1984年・80分)。
処女懐胎とキリストの誕生をテーマにした作品だが、姪を連れたガブリエルという男が飛行機でジュネーブへやってきてタクシーを乗っ取り、目的は何かと思えば、マリアに受胎告知をしにいくのである。(鈍感な私は、この男が天使であることに、なかなか気付かなかった。なんといっても羽がはえていないのだから!)。受胎告知されるのは、ガソリンスタンドの娘でバスケをやっている高校生マリア。最終的な受胎確認が産婦人科でおこなわれるというのも、あたりまえのようでいて面白い。普通の女子高生が普通のおじさんに受胎告知されたって、誰も納得できないわけだから。
納得できないのは、ボーイフレンドのヨセフも同じ。マリアにキスもしてもらえない彼は動揺し、「誰と寝たんだ?」なんて詰めよる。ヨセフは当初、ジュリエット・ビノシュ演じるジュリエットから結婚を迫られたときも煮え切らない態度でうじうじしているし、なんだかとても情けなく、リアリティのある男なのだった。
パリでの封切時には、カトリック系団体の大規模な抗議運動が起きたという、いわくつきの映画。もちろん「こんにちは、マリア」に対する抗議である。たとえマリアの下腹部のアップが少なかったとしても、キリスト誕生の瞬間に牛の出産シーンが挿入されなかったとしても、この映画が神への冒涜と受け取られたことに変わりはなかっただろう。権威とリアリティは、いつだって仲が悪いのだ。
*渋谷シネ・アミューズでレイトショー上映中
2002-09-15